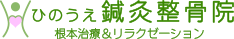
こんにちは!ひのうえ鍼灸医院です。
先週から一気に気温がぐっと下がり、半袖から上着が必要になりましたね。
稲刈りをされる田圃も見られ、ようやく秋めいてきました。
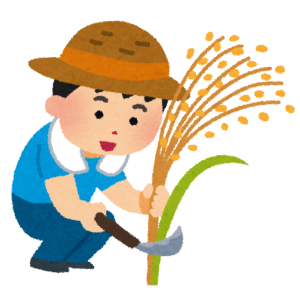
過ごしやすく、食べ物も美味しく楽しみの秋ですが、
激しい気温差で、身体が付いて行ってない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
朝晩過ごしやすくなったけど、夏バテが続いているような疲労感が・・・。
そのだるさは、「夏バテ」でなく「秋バテ」かも知れません。

夏のダメージから秋バテになってしまうのは、主に2つのタイプがあります。
夏に身体を冷やしすぎてしまったため、自律神経のバランスが崩れ血のめぐりが悪くなり、秋になって疲れやだるさ・肩こりや体調不良となって表れる。
冷房の効いた室内で過ごす時間の多かった人がなる「冷房冷えタイプ」
節電による暑さ対策のため冷たいものを摂り過ぎてしまったことによって起こる「内臓冷えタイプ」
思いつく方もいらっしゃるのではないでしょうか。
10月になっても真夏日があったり、かと思えば晩秋に近い陽気もあるなど、気温が安定しません。
日中は半袖で過ごせても、朝晩は冷えて長袖のパジャマや掛け布団が必要になるなど、温度差が激しいのもこの時期の特徴です。
こうした急激な寒暖差に対応しきれず、体調を崩しやすくなってしまうのです。
「秋の長雨」「女心と秋の空」と言われるように、天候の変化がめまぐるしく、気分も体調もなんとなく不調になります。
さらに台風の襲来で、気圧の変化による不調や、余分な体力を使うことによって疲れが残ってしまいがちなのもこの時期の特徴です。
![]()
*じんわり体を温める
夏のダメージを取り除くために、体の内外からじっくりと温めましょう。
ストレスで不調をさらに悪化させてしまうことも。「ゆったりリラックス」を心がけて、心と体をリセットしましょう。
内臓や血液、筋肉も、もとはすべてたんぱく質でできています。
これらが不足してしまうと代謝がうまくいかず、体の機能がうまく働かなくなってしまいます。カラダを温めたりリラックスすると同時に、栄養バランスの取れた食事を、しっかり3食とることをおすすめします。
忙しくて食べられない時は、プロテインやペプチドサプリ等を活用しよう。
![]()
このように、秋バテ対策は特別なことをするのでなく、じんわり、ゆったりリラックスする時間を作って、自然な回復を待つのがポイントです。
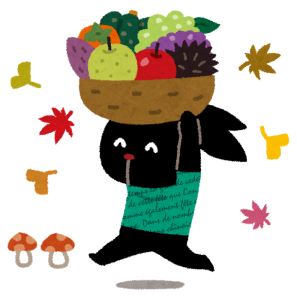
食欲の秋、行楽の秋、運動の秋、芸術の秋・・・秋は魅力がいっぱい☆
心と体に栄養をしっかり取りこみましょう。
終わってしまった夏を懐かしみつつ、存分に秋を楽しんでくださいね!

あなたは安全運転を心掛けていますか?
自分がいくら注意をしていても
巻き込まれることもありますよね((+_+))
事故に遭われて お悩みの方!
または、知り合いが悩んでいるという方!
一度、ご相談ください!!
ひのうえ鍼灸整骨院、たいが鍼灸整骨院ともに交通事故に関する相談・治療も承っております。
LINEをお使いの方は、こちらから友達登録していただき、ご案内に沿ってご予約いただければLINEからでもご予約を承れます。
お得なイベントや予約の空き情報などもお知らせしていきます!
是非ご活用ください♪
田原本 ひのうえ鍼灸整骨院
検索ID:@762zhuue
真菅 たいが鍼灸整骨院
検索ID:@662vyasq
ひのうえ鍼灸整骨院
TEL:0744-33-8304
火~土 9:00~12:30、15:00~19:30
月・日・祝日 休診
※完全予約制※

たいが鍼灸整骨院
TEL:0744-23-0399
火~土 9:00~12:30、15:00~19:30
月・日・祝日 休診
※予約優先制※

こんにちは、ひのうえ鍼灸整骨院です。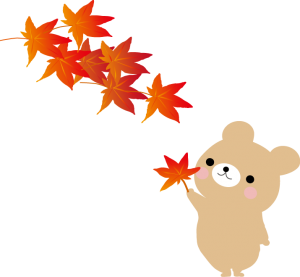
10月に入り、朝晩涼しくなったので、今回は健康維持のため簡単に出来るウォーキングについてまとめてみました。
コロナ禍で自粛生活が長期化して活動量が減り、足腰が弱くなり、わずかな段差に足を取られたりして転倒する人が急増しています。
人生100年時代とも言われ、寿命が長くなった今、いつまでも健康でいたいもの。
そこでオススメなのが、歩くこと。
いつでもどこでも手軽にできる有酸素運動です。

体を動かすこと自体が爽快感をもたらします。
景色を眺めたり季節を感じながら歩けばさらに楽しい気分になります。
歩くことで、血流が促進され脳に新鮮な酸素が供給されます。
下半身の静脈血を心臓に送る、ふくらはぎの筋肉を動かすことで、血液循環が良くなり心肺機能がアップします。
歩行などの適度な運動をした後は、心身をリラックスさせる副交感神経が、優位になり眠りにつきやすくなります。
血液循環がよくなったり、血管の弾力性が増して血圧が安定。
インスリンの働きが活発になり、血糖値が下がります
背筋を伸ばして歩くと、腰回りの筋肉が鍛えられます。
また腕振りは、肩や胸のストレッチにもなり、肩こりの改善にもなります。
歩く動作は、腸を刺激するので便秘を予防します。
また、リズムミカルな動作が、腸の動きを支配する自律神経を整えます。
歩くということは、立った姿勢をまま前へ進むこと。
正しい歩き方をすれば、自然と姿勢が良くなります。
1ヶ月続けて大きな疲れがなければ、徐々に歩数を増やしていきましょう。
腕と足の動きは連動しています。腕が左右平行になるように、かつ後ろに振ることを意識して歩きましょう。
階段は絶好のトレーニング場所、大いに利用しましょう。
肩や腰の歪みを防ぐために、鞄を片手で持つ時は、3〜5分ごとに左右持ち替えましょう。できるだけ荷物は、小分けにして両手で持ちましょう。
歩く時間を取れないという人は、目的駅のひとつ手前の駅で降りて歩く、あえて遠回りの通勤.通学ルートを選ぶ。買い物はウィンドウショッピングをするなど、日常生活の中で歩く機会を増やしていきましょう。

歩数計を装着して毎日記録すると、『今日は昨日よりもっと歩こう』などモチベーションアップにつながります。
花が美しい近隣公園を巡ったり、紅葉が見られる里山歩きを満喫する。鳥や草花の写真を撮りながら歩く、古い地図を見ながら歴史散歩するなど自分なりの楽しみを見つけましょう。
歩く仲間がいれば、互いに趣味や関心を刺激しあって新しい風景や街の様子が見えてきます。
運動による疲労を残さないために歩いた後の足のケアをしっかりとしましょう。

膝の裏側やふくらはぎをストレッチ。
特に足裏が疲れた時に効果的です。
手足の毛細血管を流れる血液が心臓に戻りやすくなる。
ふくらはぎを揉みあげることで足に溜まった老廃物や疲労物質が血流に乗って体外へ排出されやすくなります。


あなたは安全運転を心掛けていますか?
自分がいくら注意をしていても
巻き込まれることもありますよね((+_+))
事故に遭われて お悩みの方!
または、知り合いが悩んでいるという方!
一度、ご相談ください!!
ひのうえ鍼灸整骨院、たいが鍼灸整骨院ともに交通事故に関する相談・治療も承っております。
LINEをお使いの方は、こちらから友達登録していただき、ご案内に沿ってご予約いただければLINEからでもご予約を承れます。
お得なイベントや予約の空き情報などもお知らせしていきます!
是非ご活用ください♪
田原本 ひのうえ鍼灸整骨院
検索ID:@762zhuue
真菅 たいが鍼灸整骨院
検索ID:@662vyasq
ひのうえ鍼灸整骨院
TEL:0744-33-8304
火~土 9:00~12:30、15:00~19:30
月・日・祝日 休診
※完全予約制※

たいが鍼灸整骨院
TEL:0744-23-0399
火~土 9:00~12:30、15:00~19:30
月・日・祝日 休診
※予約優先制※

おはようございます!ひのうえ鍼灸整骨院です。
突然ですが、皆様は最近、音楽を聴いていますか?
テレビを観ていて流れてくるCMの音楽、スーパーなどでお買い物中に店内で流れているアーティストさんの曲やその店のテーマソング、、、などなど。
知らない間に耳から入ってきてますね。
いつの間にか口ずさんでいたりする時もあります(o^^o)
その音楽、実は私たちの心と身体にいろいろな効果があると言われているそうです!
そんな「音楽」の効果について今回は調べてみました。

動画サイトにはヒーリングミュージックと言われるジャンルがアップされていたり、音楽には人の心をリラックスさせたり癒したりする効果があると言われています。
落ち込んだり悩んだり、毎日の社会生活では気分が変化します。
そんな時、音楽を聴いて元気をもらったり、集中力が高まったり、気持ちを前向きにしてもらったりと、音楽には心を動かす力があるようです。
実は音楽のリラックス効果は科学的にも証明されているそうです!!
音楽を聴くことでどんな効果があるのかを研究している学者さんは、『音楽には心を安らかにする「セロトニン」を分泌させることができる』と述べています。
また、世界で一番リラックス効果があるといわれている「無重力」という楽曲を聴くと心拍数・血圧・コルチゾール(ストレスホルモン)を下げてくれるという効果があることが科学的に証明されているそうです。
心と身体をリラックスさせることができる音楽の効果。その効果についてまとめてみます。
激しい音楽やアップテンポの音楽、パンクロック系の音楽を聴いた時は気分が高揚しませんか?
音楽は私たちの心拍、血圧、血中の酸素量などの身体機能にも作用します。
そのため、リラックス効果のある静かな音楽、穏やかな音楽を聴いているときには、心拍数がゆっくりになって感情を落ち着かせることができます。

リラックス効果のある音楽を聴いている時、脳内では「自然の鎮痛剤」とも呼ばれている脳内物質の「エンドルフィン※」の分泌が増大。この脳内物質は、好きな人と話している時や美味しいものを食べている時などに分泌される物質と同じため、多幸感をかじさせる効果があり、ストレスを解消して前向きな気持ちにさせてくれるようです。
※エンドルフィン
脳内で機能する神経伝達物質のひとつである。内在性オピオイドであり、モルヒネ同様の作用を示す。特に、脳内の「報酬系」に多く分布する。内在性鎮痛系にかかわり、また多幸感をもたらすと考えられている。そのため脳内麻薬と呼ばれることもある。(ウィキペディア参考)
まず自律神経とは何でしょうか?
神経は『中枢神経』(脳と脊髄)と体中に張り巡らされている『末梢神経』に分けられます。
↓
『末梢神経』
①「体性神経」
→意思によって身体の各部を動かす。
例:暑いときに手で仰ぐ など
②「自律神経」
→意思に関係なく刺激に反応して身体の機能を調整する。
例:汗が出る など
↓
自律神経は、呼吸や代謝、消化など私たちの生命を維持に関わる体のさまざまな働きを支配しています。
さらに自律神経は、
「交感神経」(心と体を活動状態にする)
「副交感神経」(休息・安静状態にする)
という逆の働きをする2つに分かれます。
この2つのバランスが崩れてしまうと、神経が張り詰めた状態が続いてしまい、身体のいろいろなところに不調が現れてしまいます。
リラックス効果がある音楽には、この副交感神経を高める働きがあるので、自律神経のバランスが整っていきます。

リラックス効果のある音楽を聴くことで、
脳の働きを落ち着かせて眠気を促進する作用があります。イライラしているとなかなか寝つけません。神経が高ぶっている時、悩みごとで頭がいっぱいの時には、穏やかな音楽によって心を鎮めるため、リラックス効果のある音楽を聴いてより良い眠りを得ることが大切ですね。
音楽の効果についていかがでしたか?
音楽の力は、病院や介護施設などでも活用されているようです。音楽を効果的に用いることで身体的、精神的な痛みや辛さを和らげる「音楽療法」もありますね。
ぜひ皆さまも、元気が出る音楽、前向きに頑張れる音楽、癒される音楽など探してみてください!
LINEをお使いの方は、こちらから友達登録していただき、ご案内に沿ってご予約いただければLINEからでもご予約を承れます。
お得なイベントや予約の空き情報などもお知らせしていきます!
是非ご活用ください♪
田原本 ひのうえ鍼灸整骨院
検索ID:@762zhuue
真菅 たいが鍼灸整骨院
検索ID:@662vyasq
ひのうえ鍼灸整骨院
TEL:0744-33-8304
火~土 9:00~12:30、15:00~19:30
月・日・祝日 休診
※完全予約制※
たいが鍼灸整骨院
TEL:0744-23-0399
火~土 9:00~12:30、15:00~19:30
月・日・祝日 休診
※予約優先制※
 皆さんこんにちは。池田です。9月に入って早々に雨が降り、秋らしい気候になってきましたね。月末には夏の暑さが戻ってくるみたいですが・・・。それは置いておいて。秋といえば、読書の秋、スポーツの秋、睡眠の秋、芸術の秋、いろいろありますがなんといっても食慾の秋!!!果物も美味しいし秋刀魚なんかもいいですね~。今はコロナもありますので以前に比べハイキングや山登りなど外でお弁当を食べたりという機会は減っておりますが、実はそういうところに食中毒の原因が潜んでいるかもしれません。
皆さんこんにちは。池田です。9月に入って早々に雨が降り、秋らしい気候になってきましたね。月末には夏の暑さが戻ってくるみたいですが・・・。それは置いておいて。秋といえば、読書の秋、スポーツの秋、睡眠の秋、芸術の秋、いろいろありますがなんといっても食慾の秋!!!果物も美味しいし秋刀魚なんかもいいですね~。今はコロナもありますので以前に比べハイキングや山登りなど外でお弁当を食べたりという機会は減っておりますが、実はそういうところに食中毒の原因が潜んでいるかもしれません。
 食中毒の発生は夏だけとは限らない
食中毒の発生は夏だけとは限らない厚生労働省の『平成29年 病因物質別月別食中毒発生状況』によると、食中毒は夏以外の季節にも発生していることが分かります。
例えば、春や秋はキノコやフグなど自然毒による食中毒、夏は細菌性の食中毒、冬はノロウイルスを原因とする食中毒が多い傾向にあります。
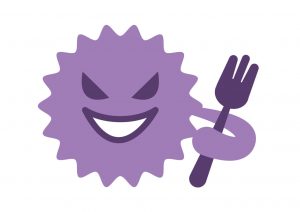 秋に気を付けたい食中毒の原因菌
秋に気を付けたい食中毒の原因菌真夏と比べると暑さが和らぐものの、9~10月も細菌を原因とする食中毒発生件数が高い季節といえます。比較的名前が知られている“サルモネラ菌”のほか、“ウェルシュ菌”と“カンピロバクター”を原因とする食中毒の発生件数は多い傾向にあるため、調理の際は注意が必要です。
ウェルシュ菌とは?
健康なヒトの腸管や土壌、下水等の自然界に広く生息する細菌です。酸素のないところで増殖し、芽胞を作ります。※芽胞は非常に熱に強い性質をもち加熱に耐えます。このため、加熱後に、室温に長時間保温された食品が原因となりやすい食中毒です。増殖する際に毒素(ウエルシュ菌エンテロトキシン)を産生します。ウエルシュ菌の産生するエンテロトキシンは易熱性のタンパク質で、熱(60℃10分)や酸(pH4以下)で容易に不活化されます。
※芽胞とは、増殖に適さない環境で生き残るための殻のようなもの。ウェルシュ菌は芽胞の状態で生き残り、食品の温度が下がると急速に増殖するという特徴があります。
カンピロバクターとは?
カンピロバクターは家畜や家禽、野生動物の腸内に生息しており、主に鶏肉に多いといわれています。
カンピロバクターは好気性でも嫌気性でもなく、酸素が5~15%ほど含まれる微好気的な条件で発育します。100個前後の少量の菌で感染し、潜伏期間が1~7日と長いのも特徴です。食肉から調理器具やサラダなどへの二次感染によって食中毒を引き起こすことが多く、感染すると腹痛、下痢、発熱などの症状を引き起こします。
食中毒を防ぐ3つのポイント
菌をつけない:調理器具や手をしっかりと洗う
菌を増やさない:冷蔵庫で保存
菌を撃退:しっかり加熱する
冒頭でも言いましたがコロナがありますのでなかなか外で食事とはいきませんが、自宅の庭などで食事するということもあるかもしれません。食中毒を防ぐ3つのポイントを守り、食中毒対策を怠らないようにしましょう。安全な調理法で食欲の秋を楽しんでいただければと思います。

あなたは安全運転を心掛けていますか?
自分がいくら注意をしていても
巻き込まれることもありますよね((+_+))
事故に遭われて お悩みの方!
または、知り合いが悩んでいるという方!
一度、ご相談ください!!
ひのうえ鍼灸整骨院、たいが鍼灸整骨院ともに交通事故に関する相談・治療も承っております。
LINEをお使いの方は、こちらから友達登録していただき、ご案内に沿ってご予約いただければLINEからでもご予約を承れます。
お得なイベントや予約の空き情報などもお知らせしていきます!
是非ご活用ください♪
田原本 ひのうえ鍼灸整骨院
検索ID:@762zhuue
真菅 たいが鍼灸整骨院
検索ID:@662vyasq
ひのうえ鍼灸整骨院
TEL:0744-33-8304
火~土 9:00~12:30、15:00~19:30
月・日・祝日 休診
※完全予約制※

たいが鍼灸整骨院
TEL:0744-23-0399
火~土 9:00~12:30、15:00~19:30
月・日・祝日 休診
※予約優先制※

ひのうえ鍼灸整骨院、竹村です。
いよいよ8月も終わろうとしていますが、皆様元気にお過ごしですか?
オリンピック、高校野球、パラリンピックとテレビで応援しながら元気をもらいましたね。
8月前半はものすごく暑い日が続き、中半は雨ばかり続きで、なかなか体にとっては過酷な環境が続きました。
ここからは夏バテにご注意ですよ!
一日しっかり仕事して、さてようやく寝れると布団に入ったのに、寝付けない…
疲れてるはずなのに眠れない…
夢ばっかり見てる感じでぐっすり寝れてない…
なんてことないですか。

今回は睡眠について西洋医学、東洋医学的に考えてみましょう!
まずは眠れない、不眠のタイプをざっくり分けてみると、
寝ている途中で目が覚めてしまうもの
多い人では1時間ごとに目が覚めてしまうケースもあります。
体内時計の乱れている方や高齢者でも多いです。
寝床に入ってもなかなか寝付けない状態のことです。
ストレスの影響を強く受けやすいといわれます。
これが繰り返されると眠れないこと自体がストレスになってますます寝付けなくなるという不眠の悪循環につながります。
朝起きようとする時間よりも2時間以上早く目覚めてしまうもので、体内時計のリズムがずれて早まりすぎている状態です。
高齢者にも多く、家族と生活リズムが合わないなんてことにつながります。
西洋医学的な睡眠研究の本としては、「スタンフォード式 最高の睡眠」(西野精治著)があげられます。
ここでは皮膚体温と深部体温の変化が入眠と関係しているという解説があります。
皮膚体温とは手足の体温のことで、日中に低く、夜に高くなっていきます。
逆に深部体温は体の内部の体温のことで、日中に高く、夜に低下していきます。
日中は深部体温が皮膚体温よりも最大で2度ほど高くなり、夜になるとだんだんとその差が縮まってきます。
そして、皮膚体温が上がり、深部体温が下がっていくと眠気が引き起こされるということです。
なかなか入眠できない方は、深部体温が高い状態で維持されてしまっていることが考えられます。
これは、東洋医学での「内熱」「心熱」の考え方と一致します。
東洋医学では、睡眠については陰陽の気の交流が重要になってきます。
それでは古典を紐解いてみましょう。
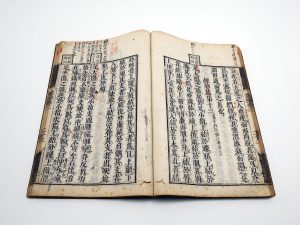
「陽気尽き、陰気盛んなれば則ち瞑(めい)す、陰気尽き陽気盛んなれば則ち寤(さ)む」『霊枢』口問第二十八
陽気が少なくなって陰気が旺盛になってきたら眠たくなる。陰気が少なくなり陽気が旺盛になってきたら目が覚める。
「黄帝曰く、病て臥すること得ざるは、何の気しからしむ、岐白曰く、衛気、陰に入るを得ず、常に陽に留まる、陽に留まれば則ち陽気満つ、陽気満つれば則ち陽蹻盛んにして陰に入るを得ず、則ち陰虚す、故に目を瞑らず」『霊枢』大惑論第八十
黄帝がおっしゃるに、病んでいるのに寝ることができないのはどういうことか?岐白がおっしゃるには、衛気(陽気)が陰の部に入ることができずに常に陽の部にとどまってしまう。陽の部にとどまったら陽の部に陽気が旺盛になり、陽気が陰の部に入ることができない。だから陰の部が虚してくる。だから目を閉じない。
昼間は陽で夜は陰ですが、身体の衛気(陽気)は昼間は陽の部をめぐり、夜は陰の部をめぐるんですね。
この陽の部とは経絡でいう陽経の通る体表面や身体の上部です。陰の部とは陰経の通るところや内臓のある部や下半身のことです。
昼間は陽気が陽の部に旺盛になり、夜になると陰の部に入る。それで眠れるようになります。
不眠は何らかの原因で夜になっても陽の部に陽気が多いことからおこります。
陽気が多くなるのは、陰の部にある陰気が弱くなって陽気と交流できないからです。
つまり、陰が虚で陽が実となっているということですね。

まとめますと、
陰陽の気の交流が過不足や停滞によってくずれる
陽気が陰の部に入れない
頭や目に陽気が残ってしまい、不眠となる
長くなったので、つづきは次回に。
肝、腎、脾の臓の症状から睡眠を考えてみましょう!
交通事故はだれにでも起こりうることです。
すべては一瞬のできごと。もし事故してしまったら…ご相談ください。

磯城郡、橿原市、桜井市、北葛城郡、などで腰痛・肩凝り・婦人科疾患・産後骨盤・子供の夜泣き・頭痛・ストレス・交通事故疾患等、でお悩みの方は、ひのうえ鍼灸整骨院・たいが鍼灸整骨院にご相談ください。
ひのうえ鍼灸整骨院 へのお問い合わせはこちらまで!!
TEL:0744-33-8304
完全予約制 になりますので、お手数をおかけしますが
メール・お電話 にて ご予約 をお取り下さい m(__)m
お電話では、当日のご予約も承っております。

たいが鍼灸整骨院 へのお問い合わせはこちら
TEL:0744-23-0399
たいが鍼灸整骨院(真菅院)は 予約優先制 です。
待ち時間を減らしスムーズに治療を受けるためにも
事前に ご予約をお取りする ことを おすすめ します(*^^*)
